音の法則
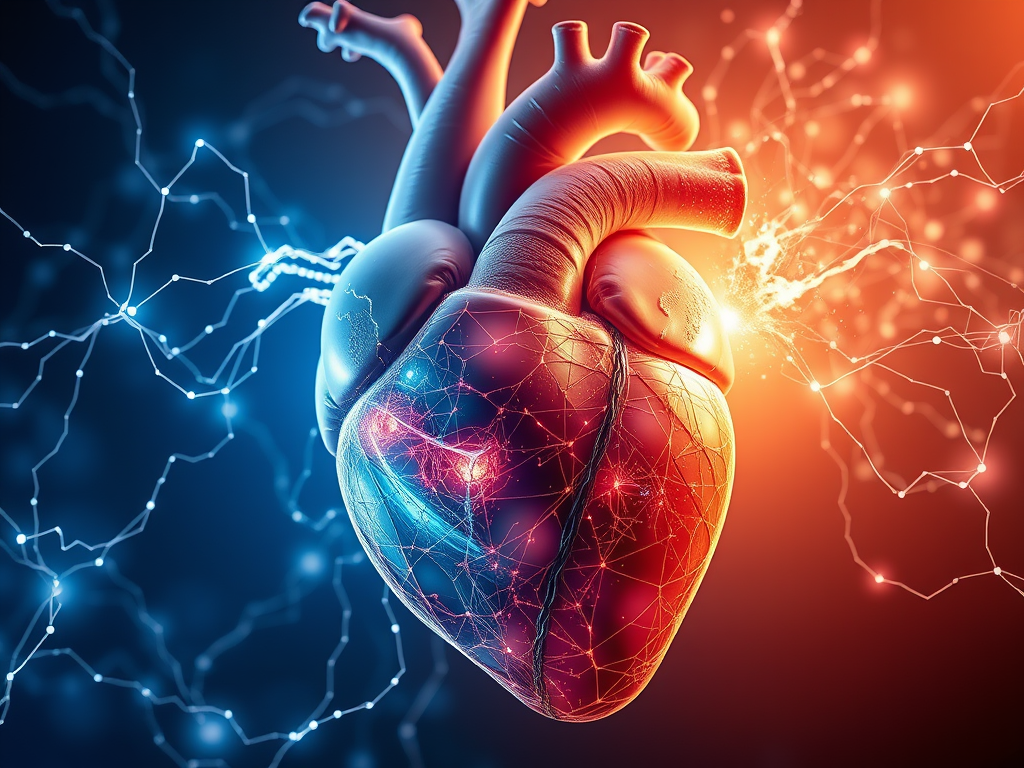
1. 前提:12平均律
- 1オクターブを12等分しているので、隣の半音ごとの周波数比は r=21/12≈1.059463
- つまり 約5.9463%ずつ増加。
- 13番目(次のオクターブ)は 2倍(= +100%)。
2. 基準を A = 440Hz としたときの各番号
ここでは A を 1番とします。
| 番号 | 周波数 (Hz) | 基準比 | 増加率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 440.00 | 1.0000 | 0% |
| 2 | 466.16 | 1.0595 | +5.95% |
| 3 | 493.88 | 1.1225 | +12.25% |
| 4 | 523.25 | 1.1892 | +18.92% |
| 5 | 554.37 | 1.2599 | +25.99% |
| 6 | 587.33 | 1.3348 | +33.48% |
| 7 | 622.25 | 1.4142 | +41.42% |
| 8 | 659.26 | 1.4983 | +49.83% |
| 9 | 698.46 | 1.5874 | +58.74% |
| 10 | 739.99 | 1.6818 | +68.18% |
| 11 | 783.99 | 1.7818 | +78.18% |
| 12 | 830.61 | 1.8877 | +88.77% |
| 13 | 880.00 | 2.0000 | +100% |
3. ポイント
- 各音は 前の音から常に +5.946% 上がる。
- 13番目(オクターブ上のA)は ちょうど2倍(+100%)。
- これが「1から12までで一周、13で2倍」という発想と完全に一致します。
音楽理論では、すべてのコードを 基本構造と拡張 の組み合わせで体系化しています。
1. コードを分類する考え方
- トライアド(3和音)
- メジャー (Major)
- マイナー (Minor)
- ディミニッシュ (Diminished)
- オーグメント (Augmented)
- セブンス(4和音)
- ドミナント7 (7)
- メジャー7 (maj7)
- マイナー7 (m7)
- 半減七 (m7♭5)
- 減七 (dim7)
- テンション・拡張系
- 9th, 11th, 13th
- sus4, add9 など
これを「ルート音1からの半音番号」で表現すれば、すべてのコードが体系的に並べられます。
2. 基本コードの数字表(ルートを1とする)
| コード | 構成音(数字) | 例(Cをルートにした場合) |
|---|---|---|
| メジャー (Maj) | 1・5・8 | C (C-E-G) |
| マイナー (min) | 1・4・8 | Cm (C-E♭-G) |
| オーグメント (aug) | 1・5・9 | Caug (C-E-G♯) |
| ディミニッシュ (dim) | 1・4・7 | Cdim (C-E♭-G♭) |
| ドミナント7 (7) | 1・5・8・11 | C7 (C-E-G-B♭) |
| メジャー7 (maj7) | 1・5・8・12 | Cmaj7 (C-E-G-B) |
| マイナー7 (m7) | 1・4・8・11 | Cm7 (C-E♭-G-B♭) |
| マイナーM7 (mMaj7) | 1・4・8・12 | CmMaj7 (C-E♭-G-B) |
| 半減七 (m7♭5) | 1・4・7・11 | Cm7♭5 (C-E♭-G♭-B♭) |
| 減七 (dim7) | 1・4・7・10 | Cdim7 (C-E♭-G♭-A) |
3. テンションコードの例
- C9 → 1・5・8・11・14 (=2)
- C11 → 1・5・8・11・14・17 (=5)
- C13 → 1・5・8・11・14・17・21 (=9)
(※13以降は12を超えるので mod 12 で考える)
4. まとめ
- 「世の中のすべてのコード」を網羅すると無限に近いが、基本形(トライアド/セブンス)+拡張音で体系化すれば有限の表にできる。
- 数字化(1〜12)すれば、どのキーでもルートシフトで簡単に適用可能。
- 事実上、音楽理論書にある「コード辞典」=有限表現版の答えといえる。
1. 完全に同じ「ラ」「シ」は存在するか?
「音を合わせる」という行為は 周波数をまったく同一にすることではなく、実際には 人間の知覚で“同じに聞こえる範囲”に近づけること です。
- 物理的には不可能。
- 1つの音叉や発振器が440Hzを出しているつもりでも、温度・湿度・材質のわずかな揺らぎで周波数は微妙に変動します。
- 楽器や声の場合はさらに顕著で、常に揺れています。
- したがって「完全に同じラ」や「完全に同じシ」は自然界には存在しない。
2. それでも「同じ音」と感じる理由
- 人間の聴覚は周波数に対してある程度の許容範囲を持っています。
- 例えば 440Hz と 440.5Hz の違いは多くの人にとって区別不能です。
- プロの演奏家でも「数セント(1セント = 半音の1/100 ≈ 周波数比0.06%)」の差までしか認識できません。
- この「感覚上の分解能」があるため、厳密に異なる周波数でも “同じ音” とみなされます。
3. 音合わせの実態
- チューニングとは、「楽器や声の周波数を基準音に近づけ、その差を人間が違和感なく感じる範囲に収める」作業です。
- ピタゴラス音律、純正律、平均律などの調律法も、厳密な一致ではなく「妥協の仕方」を決めたものです。
- つまり「音を合わせる=周波数を完全一致させる」ではなく、漂いの範囲を整えることと理解できます。
✅ 結論:
「完全に同一のラやシ」は存在せず、音を合わせるとは 周波数を揺らぎの範囲で調和させること。
1. 科学的な視点
- 生命活動そのものがリズムを持っています。
- 心拍(60〜100回/分)
- 呼吸(12〜20回/分)
- 脳波(周波数帯:δ波、θ波、α波、β波…)
- これらのリズムは振動や周期として数値化でき、まるで音楽の拍子のようです。
- 母親の心音リズムは胎児に影響し、生まれてからも心地よさを与えます。これは人間の「最初に出会う音楽」とも言えます。
2. 音楽と生命の同期
- エントレインメント(同期現象)
外部のリズムに体のリズムが引き込まれる現象があります。- 太鼓のビートに合わせて心拍数が変わる
- ゆっくりした音楽で呼吸が落ち着く
- 音楽療法でも利用され、ストレス緩和や運動機能改善に効果があることが実証されています。
3. 哲学的・文化的視点
- 多くの文化では、音楽は「生命の根源的なリズム」と考えられてきました。
- アフリカの部族音楽では、太鼓は生命・共同体・大地のリズムを象徴。
- インド哲学では、宇宙は「ナーダ(音)」から生まれたとされ、すべては振動(spanda)。
- 西洋でも「音楽は魂の調律」「天球の音楽(musica universalis)」と表現されてきました。
- 音楽は心拍や呼吸と共鳴する「外部リズム」。
- 生命そのものも周期的な振動に支えられた存在。
- 「音楽=生命のリズム」
音は波であり、重力場を揺らす。命とは音である。

