円株式が人気で円が買われたとしても、円安になってしまう理由と国富増強の3つの制約条件|通貨高∩GDP高∩株高
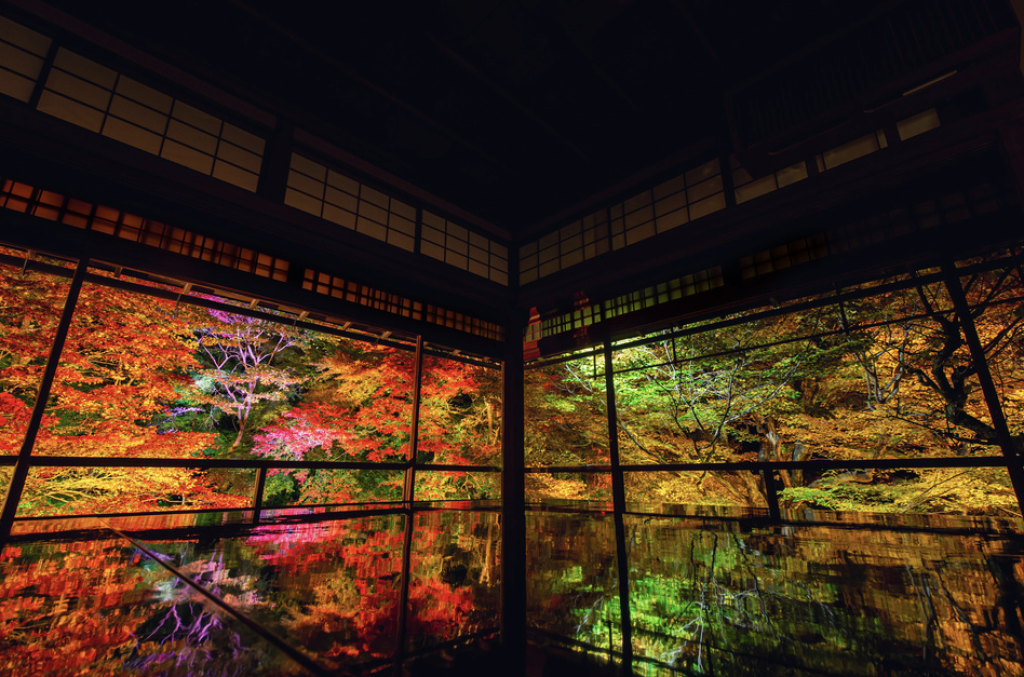
高市早苗新総裁が誕生し、日本株が株高になったが、円が買われているはずなのに為替は円安に触れた。これはなぜこうなるのか?これにはいくつかの要素が関連する。
・海外機関投資家の円買い
・ただし純粋な欧米の投資家がS&P500を買わずに日本の大型株を買うはずはないので、海外機関投資家とは、日本企業の海外支店である可能性が高く、日本の保有するドル建て対外純資産である
・ドルで払い込まれ、円が購入されるが、JPモルガンやMUFG, SMBCの日本支店において、ドルで払込された原資をもとに、円を貸し出し、円建ての株を買い、証券を保管する
・海外機関投資家は例えばニューヨークやロンドンの証券口座で日本株を管理することになる。一方で、円の為替リスクをヘッジをするために証券で円を買った分、同量の円を売る。これにより、株式によるインカム、キャピタルゲインのみを享受するというリスク切り分けができる
・結果として、ドル建てで円の株式を購入した顧客はドル→円の為替をせずに株式を購入し、円→ドルの反対為替だけをすることになるので、日本株が海外投資家に買われれば買われるほど円安が進行してしまう。
・海外機関投資家比率を高めて計画的に日本株を株高にしようとすると、この構造から逃れることができない。円を買ってもらえるタイミングが来れば良いが、株安にして為替ヘッジを解消した時にだけしか円を買ってもらえるタイミングは来ない。
・人口減少している日本において貿易収支で獲得したドルを円に転換して内国投資に振り返る大企業はいない。どちらかというと内国で稼いだ円をASEANオフショアに送金してドルに変えてしまう。資本収支も、対外的に稼いだドルやユーロを円に変えて内国投資をしようとするような企業はない。
しかし、国力の基本は通貨高、GDP高、株高という互いに逆相関してしまう数字を同時に高めていくことである。国際競争力を生み出して、海外の消費者や法人に日本円で日本の財やサービスを買ってもらうしか、これは実現できない。政策金利、長期金利を高めて通貨高にする方法はある。これは2020年代のアメリカが利用した手法であるが、これは根本的な解決策ではないため、比較的低い政策金利のもと、マネーサプライをさほど増やさずに通貨高、GDP高、株高を実現するという制約条件設定が国富の増強に必要となる。
1. 事象の観察
高市早苗新総裁の誕生後、日本株は上昇したにもかかわらず、為替市場では円安が進行した。
通常であれば、株高局面では海外投資家の資金流入により円が買われ、円高方向に動くと考えられる。
しかし現実には、株高と円安が同時に進むことがしばしば観測される。
2. 仮説:海外機関投資家の「円売りヘッジ構造」
この現象の背景には、海外投資家による日本株投資の為替ヘッジ付き構造が関係していると考えられる。
- ドル建てでの日本株購入
海外機関投資家はドルを原資に、J.P.モルガンやMUFGなどを通じて日本株を購入する。
実際の円資金は日本の銀行が立て替え、株式取引を円建てで決済する。 - 銀行による為替ヘッジ
日本の銀行は、立て替えた円の為替リスクを回避するために、FX市場で円売り・ドル買いを行う。
このヘッジ取引が円安圧力を生む。 - 投資家のリスク切り分け
投資家は株式のキャピタルゲイン・インカムゲインを享受しつつ、為替変動リスクを遮断する。
その結果、日本株買い=円売りという逆説的な構造が成立する。
3. この構造は常に成り立つか
(1) 買い主体の多様性
海外機関投資家のすべてが為替ヘッジを行うわけではなく、
一部のファンドや個人投資家は無ヘッジ運用を選択する。
また、国内投資家が主導する株高局面では、円需給が中立または円高に働くこともある。
(2) 先物・ETF経由の影響
CMEの日経先物や米国上場の日本株ETFはドル建てで取引されるため、
現物市場の円需給に直接的な影響を与えない場合も多い。
株価上昇と円相場の連動は、取引経路によって大きく異なる。
(3) 時間軸のズレ
為替ヘッジは「円売り→後日円買い戻し」という形で実行されるため、
短期的には円安が進んでも、中期的には円高に戻る可能性もある。
したがって、「株高=円安」は短期的な現象にとどまることが多い。
(4) 外部要因の支配
近年の為替相場は日米金利差や原油価格、米国経済指標に強く依存しており、
国内の政治イベントよりもこれらの要因が優先して為替を動かすケースが多い。
したがって、株高円安の関係は構造的必然ではなく、条件付きの相関である。
4. 日本経済の構造的課題
人口減少と企業の海外投資志向により、
日本の貿易黒字や対外純資産で得たドルが国内投資に還流しにくくなっている。
多くの企業はむしろ国内で得た円をASEANなどのオフショア市場へ送り、ドルに転換している。
このため、資本収支面でも円の需給が恒常的に弱い構造が生まれている。
5. 国富の形成に必要な条件
真の国力は、通貨高・GDP高・株高の三要素を同時に実現することで生まれる。
そのためには、金融緩和や金利操作による一時的な円安・株高ではなく、
生産性向上と国際競争力の強化によって、海外の消費者や企業が円建てで日本の財・サービスを購入する経済構造を築くことが不可欠である。
金利引き上げで通貨を強くすることは一時的な手段であり、
むしろ低金利のままマネーサプライを膨張させずに
実力で通貨高・成長・株高を同時に実現することが、
持続的な国富の増強に不可欠な政策課題である。
✅ 結論
「株高になると円安になる」という現象は、海外投資家のヘッジ構造と金融市場の制度的要因によって短期的には合理的に説明できる。しかしそれは普遍的な法則ではなく、日本経済の構造的な資本還流の弱さと国際金利環境に依存する条件付き現象である。長期的な国力強化には、通貨高を恐れずに生産性と付加価値の高い成長構造を築く必要がある。

