スタートアップ経営者が最低限持つべきメンタリティ|指針を示して、指示出さず
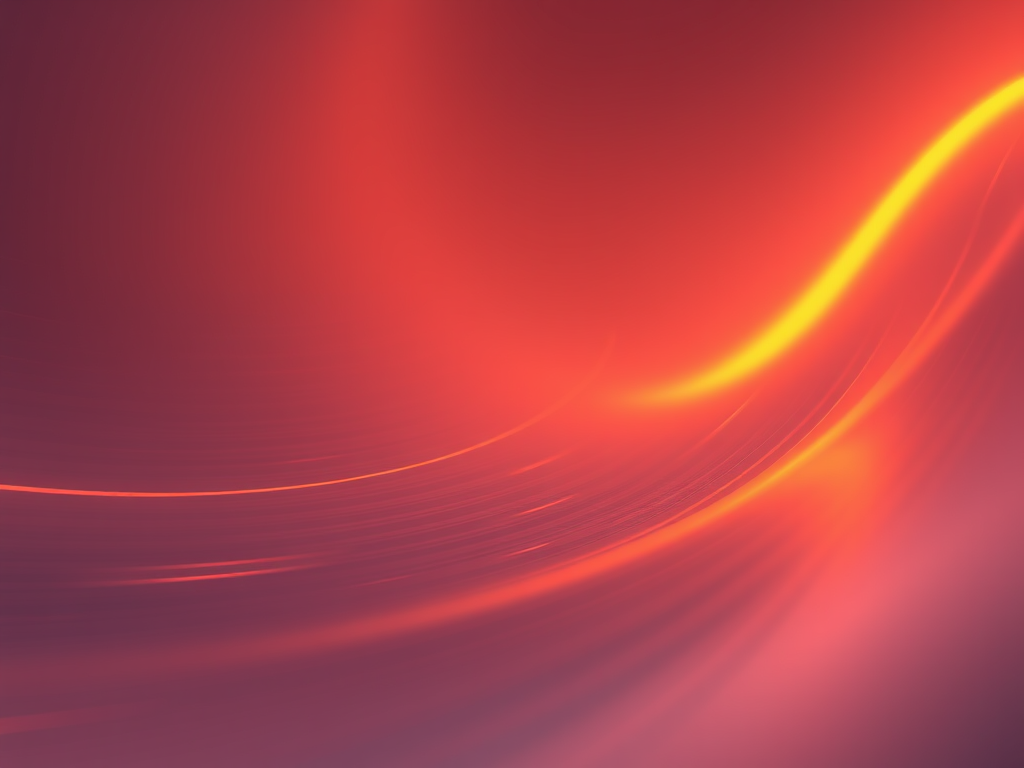
スタートとゴールを決めると経路は自動選択される
スタートアップのリーダーは最適化問題を解いてはならない。始点と終点を決めることこそがもっとも重要なアクションであり、問いの設定は代替が効かない。
内発的意思発信による制約条件付きゴール設定は代替が効かない一方で、膨大な計算資源を必要とする最適化問題は基本的には自然界が解いてくれるといっても過言ではない。地球を含む恒星系や惑星系は計算資源なのである。スタートアップが時価総額100兆円になるまでの経路において、スタートとゴールさえ決めれば経路は自動選択されるというのが信じられない人は多いと思うが、宇宙のスケールから見たら一瞬で選択されているように見えるはずである。
指針を示して、指示出さず|組織のリーダーは経路最適化問題を解いてはならない
組織のリーダーが経路最適化問題を解き始めると必ず消耗する。組織のトップが経路最適化問題を取り組み始めた時点で既にその組織は負けているといえる。
組織のリーダーは、経路最適化問題は解かず、ゴールに向けたブレイクスルーの初動にだけ力を貸すことが重要である。ブレイクスルーは労力(労働時間)ではなく構造に由来するため、ブレイクスルーを生み出す最低条件(Minimum set of truth)とは発見そのものに対する労力貢献ではなくゴールの制約条件設定であり、イノベーションフレームワークの設計指針のプロンプトを示すことが必要なアクションである。(設計そのものに取り組むことはMinimum set of truthではない)
ブレイクスルーを生み出す最低条件(Minimum set of truth)
経営者はスタートからゴールに向かう制約条件の設定(フレームワークの設計指示書)に力を貸すことを最優先にすべきであり、イノベーションそれ自体の発明者(最適化問題の計算者)になる必要はない、むしろなってはいけない。発明とは文化のようなものであり、祭りのように自然発生的なものである。祭りを企画してイベント企画会社になろうとしても、自然発生的なコミケには勝てないということである。ましてや、組織のリーダーが祭りの企画推進者になってはならない。コミケのスタートとゴールについてはよく知らないが、私たちが住みたい街を作るという、Universityができた理由と同様のスタート(内発的動機)とゴール(設計指示文)があるはずである。
問いの設定=プロンプト
リーダーは設計をする必要がないからといって設計指示書を出さなくて良いわけではない。設計指示書と設計作業は別物である。設計作業は指示書がないと始まらない。始点がないと終点がないのである。つまり、経営は常に自分から発信するものである。よく、スタートアップは走りながら解決するという言葉があるが、走りながら解決できることはさほど多くはない。始まりと終わりが決まると、途中経過もある程度の確率で決まるので、走りながら変わることはない。待っていても何も変わらないのである。待っていれば何かが変わるというのは勘違いであり、ほとんどのケースで結果は決まってしまっているので待つことに意味はないのである。出した指示が機能しているかは通常2、3日で回答が来るものである。
誰かが提示した問題に巻き込まれていないか?
発明のように、出された指示に対して最適化問題の計算者というポジションは、あらゆる人にとって魅力的である。数学の未解決問題も、始まった複雑な謎を最後に解くのは自分だと言わんばかりに、あらゆる数学者が挑戦する。受験も、出された問題に回答するルールであり、受験生はみんなテストを受けに来る。問題を出す側は色々考えないといけないので大変である。問題を回答する側は比較的狭い範囲を考えれば良いので、完全性(まるかばつか)を味わうことができるので魅力的である。
問いの源は常に自分から発信されなければならない
スポーツ選手になりたがる人は多くても、金の出し手であるスポンサーになりたいと憧れている少年少女は少ないだろう。接触回数、露出回数が多いとなにかをやっているように見えるし、誰よりも考え、素早く物事を処理しているように見えるからである。しかしそれはCPUの演算処理の部分を担っているに過ぎず、稼働率が高いエリアというのは、実は全体としてはバランスが悪い部分として目立つのである。
集中処理以上に重要なのが負荷分散であり、ロードバランシングの機能がないとスケーラブルにならない。したがって情報処理屋さんは貧乏暇なしになる。出された指示に対して計算資源を使っている状態なのではないか?今消耗戦をしてしまっているのではないか?自分自身から市場に対してプロンプトを出せているか?これらの問いについて自問自答し、自分自身が何かの発信者に巻き込まれていないかどうか常にリーダーは力の源に対して敏感になる必要がある。
トップラインを伸ばすこと vs ボトムラインの底上げ の矛盾
リーダーがとるべきもっとも重要な仕事はトップラインを伸ばすことと、ボトムラインを底上げすることの矛盾する2点を同時に実行することである。トップパフォーマーを生み出すトップ集団のパフォーマンスベンチマークやハードルレート(足切りライン)を設定し、トッププレイヤーのために青天井を作り上げることである。自分自身がトッププレイヤーになることではない。リーダーに必要なのは、能力で他人を凌駕することではなく、能力がなくても負けない対抗要件を得るということである。
対抗要件を支持すればトップとボトムはどちらも取れる
対抗要件とは理解しにくい概念であるが例えば不動産の所有権登記で対抗要件という単語が用いられる。enforceability against third parties、perfection of rightsと英訳できるが、第三者の主張に対して正当性を主張できる根拠のことである。strategic counter-condition(戦略的対抗条件)とも言い換えれるかもしれない。例えば、人材育成をするとすぐに独立される業界があるとしても、代替人材をすぐに取れる会社であれば問題はない。辞められて困るのは辞められて困るくらいに、あらゆる経営アクションが後手に回っているからである。トップ人材が集まる風土を作るとともに、誰にいつ辞められても大した影響はないくらいの状態にしておくこと。つまり、トップラインを伸ばすことと、ボトムラインを底上げすることは矛盾しているように見えるが、実は弱点がない状態(対抗要件)を作ることを中心と据えれば、トップを伸ばすことと、底上げすることが同じアクションになるのである。
Weakest Link Theory
トップパフォーマーを伸ばす一方では組織の隅々に蔓延する律速(weakest link)を特定することが同時に必要となる。
An organization is only as strong as its weakest link.The weakest link defines the real strength of any organization.
もっとも弱い鎖が組織の強さの限界であり、企業は強さで勝つのではなく弱点がないことにより勝つ。
この律速(ボトルネック)は組織のあらゆるところに生じる。弱点は販売、マーケティング、生産、設計、開発、法務、労務、税務、会計、財務、英語、ハードウェア、ソフトウエア、各種言語、食糧、資源、軍事、政治などのあらゆる局面に生じる。そしていざとなれば、その役割を演じる可塑性を持っている必要がある。
生物はコモディティで構成されている
極論をいってしまえばリーダーはエコシステムのすべての領域に神経が通っている必要があるし、全ての組織を構成するための最小条件を具備しなければならない。体には、ここだけはなくてもよいという組織がないのと同様に、組織のトップが経済界で求められるすべてを備えていない場合、その部分が重大なリスクとして常に健在化しており、見る人が見れば、明らかな律速として成長をさまたげているのがわかるのである。同時に、体の構成単位はミトコンドリアなどのコモディタイズドされた構成要素であり、その原料もタンパク質(炭素 (C)、水素 (H)、酸素 (O)、窒素 (N) )などの宇宙空間における元素質量の低いコモディティ群である。
心の隙が負けを呼び込む
すべてを把握し、全てに代替し、あらゆるものの構成要素になれるようにするというメンタリティ前提は時間、資源は限られている人間には厳しいものがある。これは自分の心のとの戦いになる。「他の人よりできてるからいいんじゃないか?」とか「さすがにここまでやらないでも十分ではないか?」という甘い気持ちが負けを呼ぶ。
基本的に生き物は完全でないと機能しないのである。宇宙において生き物が生きられるハビタブルゾーンの制約条件は時速200kmで運転しながら、窓から右手を出して針の穴に糸を通すこと(以上に)小さな確率で成り立っている。
限られた寿命で、全宇宙を知ろうとする試み
限られた寿命で期限付きの命を前提として、宇宙のすべてを把握しようというのが経営の試みである。一つ一つのことを事細かに知りつくし、把握しつくす一必要があるにもかかわらず、一つ一つの細部にのめり込んではいけない。したがって見ているようで、見ていないという状態をつくる必要があるし、会社がどんなに大きな成果を出したとしても、一瞬の達成感を深く味わった上で素通りする必要がある。
嬉しさ、悲しさ、怒り、楽しさなどさまざまな感情をもとめて経営を始める人がいるかもしれないが、感情的報酬を経営に求めるのはおすすめしない。
経営は経済の下位集合、個は種の下位集合
経営は経済の下位集合であり、上位に位置する経済の本質は代替可能性、スケーラビリティ、力の統一理論である。真実を求め、局所的な整合性、広域整合性、大域整合性と、経済は自律的に成長していく。個の尊重は種の生存の下位概念なのだ。人は誰しも自分は特別だと思いたがるが、自分だけは特別だという思想は経済に反する。
経済の世界では「うちの業界は特殊だ」「うちの業種は特殊だ」という自分だけは特別だという言い訳は通用せず、あらゆる産業、職業が資本収益という唯一の評価指標(財務健全性、資本収益性、成長性)でランク付けされる。また経歴、スキルも関係ない。経営の世界においては門外漢であっても、自分はまだ経験が少ないから許されると考えているうちはなにも大成しないのである。セルフハンディキャッピングは経営の最大の敵である。40℃の熱があってもプロであるなら試合に負けることは許されないのだ。たったひとつの言い訳が取り返しのつかない敗北を生むことになる。
売上がゼロでも初日から一国一城の主
もし社長の位置についたなら、売上がゼロでも初日からあなたが一国一城の主である。日本で起業するのであれば、挑戦者として伝統的最大手のトヨタ自動車の社長と戦って、丸腰で勝たなければならないのである。社長であるにも関わらず、アップルやマイクロソフトの社長に会って緊張するようでは、心構えがなっていないということになる。
有名人に会って写真を撮って喜んでいるようなメンタリティでは、会った瞬間に負けということになる。世界中のビリオネアに、持たざる挑戦者として「いかに丸腰で最強の敵に勝つか?」そのゴール設定を持っていない場合、スタートアップの経営者は大成しないだろう。
もっとも強い敵に勝つという大義名分がないのであれば、スタートアップを始めた理由が「他でうまくいかなかったから」というだけになってしまう。始めた理由の後ろめたさを上書きするには勝つしかないのである。
意思は資本の上位集合である
意思は資本の上位集合である。資金、資源、人材、利益、フリーキャッシュフローなどあらゆるマテリアライゼーションは、ある人が発する意思(Attention)からゴール(Materialization)を設定した後に自然現象として発生する経路最適化問題において、外圧に対するロバストネスをもった最速降下曲線(ブラキストクロンカーブ)の周辺のノイズなのである。つまり、意思は経済の上位集合であり、経済の戦いは、意思の戦いの代理戦争である。
経営者がスタートとゴールの設定に特化し、経路最適化問題を放棄すれば目標は上振れする
経路最適化問題は経営者の仕事ではない。この命題の意味するところは大きい。つまり、スタートとゴールさえ設定すれば、どんなに困難で複雑な道のりに見えても、目標は上振れ達成するということなのである。
計画とは支配であり、支配には限界がある。創発とは信頼である。経営者は未来を設計するのではなく、未来が自己設計できる完結構造の信頼確証者である。したがって、「経路最適化を放棄する者だけが、最終的に最適解を得る」ことになるのである。
経路選択、経路最適化の放棄は目標達成の必要十分条件である。
Regret Minimization Theory
HITSERIES CAPITALの投資方針はRegret Minimization である。限界IRRとは「選択の後悔を最小化するための、未来における回収率」を測定するための観測モデルである。一度きりの人生で、人生の生産性を最大化するためには、選ばなかった構造を観測可能にする知的射程が必要であり、人生の効率とは、「人生を何度も繰り返さなくても一度目の人生を外部評価できる構造」の観測能力に比例する。
Attention Action Alignment
スタート、ゴール、経路最適化の3点が一度きりの人生における自由意思の効果最大化に必要不可欠な要素である。経路最適化が最も計算資源を使うので、3点問題に取り組むより、スタートとゴールの2点問題に経営リーダーは特化すべきと思うが一方で、外部から経路最適化を観測するモデルさえもっていればスタート、ゴールすら設定しなくてもコンペティションでよいスタートとよいゴールを持っている選択肢が浮き彫りになって浮上してくるのである。(NYSE, NASDAQなどのエクスチェンジがそうである。)したがって、スタート、ゴール、経路の外部からの観測モデルを確立すると逆説的に実はスタートとゴールすら決めなくてもよいという結論となる。わたしは起業するとか、ビジョンがあるとか、世界一になるなどの制約条件を決めなくても、人間の本能がよりよい選択肢を社会のカオスの中からノイズを除去して自動選択することになるのである。圏論、集合論的に論理を組み立てると、実は選ばなかった人生と選んだ人生を等価にし比較評価できる。これこそが現象を的確に見極めることで、スタート、ゴール、経路に3点に対して発動することのできる最小作用干渉モデル(Attention to Materialization)である。

